ロボット・メカトロニクス学科 横山教授が「パワー・エレクトロニクス・サミット2022」で受賞者特別講演

未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科の横山智紀教授が、パワエレ分野において革新性と実用性を備える研究開発を行う研究者を表彰する「パワー・エレクトロニクス・アワード2022」にて読者賞を受賞しました。
12月16日(金)開催の「パワー・エレクトロニクス・サミット2022」(主催:日経エレクトロニクス、日経クロステック)にて、贈賞式と受賞者講演が行われます。オンラインで視聴が可能です。ぜひご覧ください。
釜道紀浩教授らの共同研究が複数のメディアに掲載

釜道紀浩教授が理化学研究所および奈良先端科学技術大学院大学と共同開発を行なった圧力駆動型ガラス発電機に関する記事が複数のメディアに掲載されました。
媒 体:日刊工業新聞社 2022年 10月 24日 朝刊 20面
Yahoo!ニュース(ニュースイッチ) 2022年 10月 24日 配信
MIT Technology Review Japan
fab crossエンジニア
マイナビニュース
タイトル:「ガラス微細流路で発電 サムスンなど 水を流すデバイス」(日刊工業新聞社)
「理研など開発、ガラス微細流路に水を流して発電するデバイスの仕組み」(Yahoo!ニュース)
「ゆっくりした動きで発電するウェアラブル発電機=理研など」(MIT Technology Review Japan)
「微細ガラスフィルターを用いた小型環境発電機を開発 理研など研究グループ」(fab crossエンジニア)
「理研など、歩行などの振動で環境発電できる圧力駆動型ガラス発電機を開発」(マイナビニュース)
圧力駆動型ガラス発電機の開発

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター集積バイオデバイス研究チームの田中陽チームリーダー(研究当時)、ヤリクン・ヤシャイラ客員研究員(奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科物質創成科学領域生体プロセス工学研究室准教授)、東京電機大学未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の釜道紀浩教授らの共同研究グループは、ガラスと水の電気的相互作用を利用し、圧力で水を流すことで電力発生可能な圧力駆動型の小型発電機を開発しました。
本研究は、科学雑誌『Scientific Reports』オンライン版(10月20日付:日本時間10月20日)に掲載されます。なお、理研は「発電デバイスおよび発電方法」として特許を出願しています。
タイトル: A pressure driven electric energy generator exploiting a micro- to nano-scale glass porous filter with ion flow originating from water
著者名: Yo Tanaka, Satoshi Amaya, Shun-ichi Funano, Hisashi Sugawa, Wataru Nagafuchi, Yuri Ito, Yusufu Aishan, Xun Liu, Norihiro Kamamichi, Yaxiaer Yalikun
雑誌: Scientific Reports
DOI: 10.1038/s41598-022-21069-8
記事リンク先:https://www.nature.com/articles/s41598-022-21069-8
https://www.dendai.ac.jp/news/20221020-01.html
ロボット・メカトロニクス学科 横山智紀教授らの研究が 日経エレクトロニクス「NEパワー・エレクトロニクス・ アワード」にノミネート

ロボット・メカトロニクス学科 横山智紀教授らの研究が日経エレクトロニクス「NEパワー・エレクトロニクス・アワード」にノミネートされました。 ノミネートについて、日経エレクトロニクス及び日経クロステックに掲載されました。
媒 体:日経エレクトロニクス9月号
媒 体:日経クロステック
タイトル:パワエレアワード2022「超高速制御でトレードオフを克服 デバイス高速化とFPGAが後押し」
掲 載:ロボット・メカトロニクス学科 横山智紀教授
ロボット・メカトロニクス教科書『メカトロニクス概論』改訂3版
2022年6月8日、ロボット・メカトロニクス学科の教員が中心となり執筆したロボット・メカトロニクスの教科書の改訂3版が発行されました。
出版社の書籍紹介より
—
最新事例まで含めてメカトロニクスを概観できる定番教科書。さらなる充実の改訂3版! ロボット・メカトロニクス関連学科を対象とした教科書シリーズの1巻として発 行し、好評を博した教科書の改訂3版。改訂2版発行から7年が経過し,この間 ヒューマノイドロボットやEV技術などの技術進展には著しいものがあります。ま た、5Gや人工知能などの周辺分野との関連についても学ぶことが必要となってき ました。今回の改訂では、図や写真を多用した解説、各章冒頭の「学習のポイン ト」、章末の「理解度チェック」「演習問題」など、読者が理解度を確認しなが ら読み進められる構成は活かしつつ、前記の事項を踏まえて全体的な内容の見直 しを図り、より時代に即した教科書となるようまとめました。
—
出版社:オーム社
書籍名:ロボット・メカトロニクス教科書『メカトロニクス概論』改訂3版
画像認識型自動除草ロボットの研究が雑誌「農耕と園藝」に掲載

農耕と園藝2022年夏号に、釜道紀浩教授の画像認識型自動除草ロボットの研究が紹介されました。また、同雑誌に、本年2月に開催したスマート農業シンポジウムの取材記事も掲載されています。
媒 体:農耕と園藝2022年夏号
タイトル:クローズアップ! 農業最新技術
記事リンク先:https://karuchibe.jp/magazine/2022%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%8f%b7/
ロボット・メカトロニクス学科 中村明生教授が日刊建設工業新聞、日刊建設通信新聞に掲載

ロボット・メカトロニクス学科 中村明生教授の研究開発テーマが、国土交通省 関東地方整備局の「令和3年度 大学等研究機関との技術(シーズ)マッチングに関する公募(第2回)」に採択され、日刊建設工業新聞、日刊建設通信新聞に掲載されました。
媒 体:日刊建設通信新聞 11月24日
タイトル:整備局が採択 CO2削減、DX推進の3件 研究機関対象にマッチング
媒 体:日刊建設工業新聞 11月24日
タイトル:3件の共同研究採択 関東整備局 戻りコンの資源化など
ロボット・メカトロニクス学科の中村明生教授が交通誘導警備システムの開発に協力

ロボット・メカトロニクス学科の中村明生教授が、企業との共同研究で交通誘導警備システムの開発に協力しました。
スマート農業シンポジウム ~加工・業務用野菜の機械化一貫体系とサプライチェーン最適化~を開催しました

東京電機大学(学長 射場本忠彦)の釜道紀浩 教授(未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科)を代表者とする「埼玉加工・業務用野菜スマート農業実証コンソーシアム」が、オンライン配信(Zoom ウェビナー)にて、「スマート農業シンポジウム~加工・業務用野菜の機械化一貫体系とサプライチェーン最適化~」を開催しました。
東京電機大学・釜道紀浩准教授が代表者を務めるコンソーシアムが採択 農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」

東京電機大学(学長 射場本忠彦)の釜道紀浩准教授(未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科)を代表者とする「埼玉加工・業務用野菜スマート農業実証コンソーシアム」が、このたび、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」(事業主体:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)の委託先として採択されました。
JAXA研究提案募集に藤川太郎准教授の研究テーマが採択

東京電機大学(学長 射場本忠彦)の藤川太郎准教授(未来科学部ロボット・メカトロニクス学科)の研究テーマ「広域探査および通信網確立のための羽ばたき移動体の開発」が、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)の宇宙探査イノベーションハブが実施した「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーションハブ」に関する研究提案募集(第5回)において、採択されました。
ロボット・メカトロニクス学科「知能機械システム研究室」が雑誌OplusEに掲載

11月25日発売の光と画像の技術情報誌「OplusE」に、ロボット・メカトロニクス学科の「知能機械システム研究室」が紹介されました。
大学の研究室の研究テーマなどを中心に紹介する、研究室探訪というコーナーで指導教員の中村明生 教授と3つの研究テーマが掲載されました。
媒 体:OplusE 2019年11・12月号(第470号)
タイトル:研究室探訪vol. 12[東京電機大学 知能機械システム研究室(中村研究室)]
掲 載:知能機械システム研究室(中村明生 教授)
記事リンク先:https://www.adcom-media.co.jp/laboratory/2019/11/25/32985/
釜道准教授が理化学研究所と共同でプレスリリースを発表

タイトル:ミミズで弁をつくる -化学刺激によるミミズ筋肉の持続的収縮を用いた弁(バルブ)-
掲 載:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 釜道紀浩准教授
記事リンク先:https://www.dendai.ac.jp/news/20190708-02.html
学科カリキュラムに関する花崎泉教授のインタビューが教育学術新聞に掲載

媒 体:「教育学術新聞」 5月15日
タイトル: 全教員でゼロからカリキュラムを構築 -迅速な教員間の情報共有-
掲 載:未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 花崎泉教授
藤川准教授が開発している蝶型はばたきロボットが「産経新聞」に掲載

5月12日の「産経新聞」に、藤川准教授が開発している蝶型はばたきロボットが掲載されました。
媒 体:「産経新聞」 5月12日
タイトル: チョウの舞は効率的 生き物に倣う
掲 載:未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 藤川太郎准教授
井上助教の開発した足底部背屈下肢装具が「毎日新聞」他各紙に掲載

井上助教の開発した足底部背屈下肢装具が「毎日新聞」他各紙に掲載されました。
媒 体: ・「熊本日日新聞」5月19日 「東奥日報」5月13日 「信濃毎日新聞」5月10日 「茨城新聞」5月9日 「山形新聞」5月6日 「岐阜新聞」5月6日
・「新潟日報」5月6日 「神奈川新聞」4月29日 「下野新聞」4月23日 「高知新聞」4月19日 「毎日新聞」4月18日 「中国新聞」4月13日 「埼玉新聞」4月10日
・「徳島新聞」4月10日 「福島民友」4月8日 「山陽新聞」4月7日 「神戸新聞」4月1日 「宮崎日日新聞」4月1日
・デジタル毎日新聞
・47NEWS
タイトル: 病 それから 工学で障害者応援したい
掲 載:未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 井上淳助教
参 考:JST 新技術説明会 https://www.youtube.com/watch?v=F9cH-Xovs0M&feature=youtu.be
藤川助教が開発したはばたきロボットが「日本経済新聞」および「化学工業日報」に掲載

2月18日の「日本経済新聞」および2017年11月16日の「化学工業日報」に、藤川太郎助教が開発した蝶をモデルとした小型はばたきロボットが掲載されました。
このロボットの研究は、今後超小型のアクチュエータやバッテリー、カメラ、センサなどを搭載し、災害現場におけるがれきの隙間など狭隘空間での観測システムなど、5年以内の実用化を目指しています。
媒 体:「日本経済新聞」 2月18日
「化学工業日報」 2017年11月16日
タイトル: 生物に学ぶロボット① 高度な制御装置なしで飛行(日本経済新聞)
東京電機大 蝶のように舞うドローン試作(化学工業日報)
掲 載:未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 藤川太郎助教
参 考:一押しシーズ> 蝶をモデルとした小型はばたきロボットの開発
中村准教授「IoT Today」に掲載

中村准教授と修士2年の阿部さんの研究がIoT Todayに掲載されました。コンピュータビジョン技術について紹介されています。
媒 体:IoT Today 9月22日
タイトル:ロボットが人間を超える“目”を持つ日 東京電機大学が開発を進めるコンピュータビジョン技術
掲 載:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 中村明生准教授
記事リンク先:http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51134?utm_source=gunosy&utm_medium=feed&utm_campaign=link&utm_content=title
IoT Today:http://iottoday.jp/
岩瀬准教授のドローンの研究実験が新聞各紙に掲載

平成27年度から埼玉県産学連携研究開発プロジェクト補助事業に採択されている、「サステイナブルなエネルギー・炭素循環を支えるスマートフォレストIRT」(研究代表:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬将美准教授)の一環で、エンジン型ドローンのフライト検証実験を7月9日、10日に長野県下諏訪で実施しました。その様子が新聞各紙に掲載されました。
実験は、共同研究開発先のインダストリーネットワーク株式会社と、岩瀬准教授の研究室の学生5名が中心になって行われました。
媒 体:信濃毎日新聞 「長く飛ぶドローン 飛行実験(岡谷の企業など共同開発)」7月11日
長野日報 「エンジン型ドローン 飛行テスト(産学連携プロジェクト)」7月11日
下諏訪市民新聞 「エンジンドローン 赤砂崎で実験」7月11日
出 演:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬将美准教授
情報駆動制御研究室 http://www.fr.dendai.ac.jp/lab/iwalab
中木元 勇希さん、吉田 伊織さん、高際 修平さん、矢部 達馬さん、佐藤 勝さん
岩瀬准教授のドローンの研究が「日本経済新聞 電子版」および「日経産業新聞」に掲載

平成27年度から埼玉県産学連携研究開発プロジェクト補助事業に採択されている、「サステイナブルなエネルギー・炭素循環を支えるスマートフォレストIRT」(研究代表:岩瀬准教授、共同研究メンバー:中村准教授、釜道准教授、岩井准教授、藤川助教)の一環で、森林調査を行うエンジン型ドローンについて、「日本経済新聞 電子版」と「日経産業新聞」で紹介されました。
媒 体:日本経済新聞 電子版 「林業、障害物回避… ドローンに使いこなし革新」3月28日
日経産業新聞 「ニュースこう読む ドローン革命使い手から 材木資源量や害獣の数把握」4月4日
出 演:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬将美准教授
情報駆動制御研究室 http://www.fr.dendai.ac.jp/lab/iwalab
共同研究メンバー:中村明生准教授、釜道紀浩准教授、岩井将行准教授、藤川太郎助教
岩瀬准教授のドローンの実験が各メディアで紹介されました

平成27年度から埼玉県産学連携研究開発プロジェクト補助事業に採択されている、「サステイナブルなエネルギー・炭素循環を支えるスマートフォレストIRT」(研究代表:岩瀬准教授、共同研究メンバー:中村准教授、釜道准教授、藤川助教)。その森林調査を行うエンジン型ドローンの実験について、下記メディアで紹介されました。
テレビ:SBCニュースワイド(信越放送)「ドローンに乗せたセンサーで森林を計測・岡谷で実証実験」12月9日
新 聞:長野日報 「エンジン型ドローンで森林3次元データ計測」12月10日
岡谷市民新聞「ドローンで立木の形状測定 森林の計測 実用化へ前進」12月10日
信濃毎日「木が茂る斜面 計測実証実験」12月10日
出 演:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬将美准教授
情報駆動制御研究室 http://www.fr.dendai.ac.jp/lab/iwalab
共同研究メンバー:中村明生准教授、釜道紀浩准教授、藤川太郎助教
釜道准教授「科学新聞」「化学工業日報」に掲載

理化学研究所と共同開発した「ミミズの筋肉組織を利用した小型ポンプ」が紹介されています。
媒 体:科学新聞 10月28日
タイトル:ミミズの筋肉使った小型ポンプ
媒 体:化学工業日報 10月19日
タイトル:ミミズの筋肉で超小型ポンプ
釜道准教授「日刊工業新聞」に掲載

理化学研究所と共同開発した「ミミズの筋肉組織を利用した小型ポンプ」が紹介されています。
媒 体:日刊工業新聞 10月19日
タイトル:ミミズの筋肉組織を利用した小型ポンプ
掲 載:未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 釜道紀浩准教授
記事リンク先:https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00403547
http://web.dendai.ac.jp/news/20161017-04.html
藤川助教「電子デバイス産業新聞」に掲載

藤川助教が開発を進めている、蝶の羽ばたきを再現した小型ロボットが紹介されています。
媒 体:電子デバイス産業新聞
タイトル:蝶の羽ばたき再現 ロボで同サイズ・質量に
井上助教 テレビ東京「生きるを伝える」に出演
(2016年 9月2日 BSジャパン)

井上助教が開発したリハビリ支援のための歩行補助器や,大学生のときにかかった脊髄腫瘍のリハビリとそこから研究者を目指したきっかけなどについて放送されます。
放送日時 : 8月27日(土) テレビ東京 午後8時54分
9月2日(金) BSジャパン 9時54分
汐月教授 井上助教 「NHKWorld」に掲載


未来科学部の講義の一環で行っている「ニーズ&アイデアフォーラム(NIF)」が紹介されました。
NIFは国立障害者リハビリテーションセンターと共同で行っている、工学系・デザイン系・福祉系の大学・高等専門学校の学生らによる福祉機器を開発するプロジェクトです。本学からは未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の汐月哲夫教授、井上淳助教、学生7名が参加しました。
この模様はNHK WORLDラジオでも紹介され、以下の記事リンク先において聞くことができます(音声は英語のみ)。
媒 体:NHK WORLD 7月26日
タイトル:Supporting Disabled Living through Youthful Ideas
掲 載:東京電機大学未来科学部
記事リンク先 : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/focus/201607220557/
ニーズ&アイデアフォーラム(NIF) : http://www.rehab.go.jp/ri/event/NIF/
石川教授「日経産業新聞」に掲載

石川教授らが開発を行なった、人間の腕の筋肉の電位を読み取り、指を曲げるなど細かな動きを判別するシステムが紹介されています。
媒 体:日経産業新聞
タイトル:腕の動き、AIで分析 細かく動く電動義手へ
井上助教 「読売新聞」に掲載

開発を行ったリハビリ支援のための歩行補助器と、開発の背景が紹介されています。
媒 体:読売新聞
タイトル:片手でつえ 歩行訓練器 「まひ悩む人の助けに」都城の病院が協力
記事リンク先:https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160606-OYTET50024/
「第9回八光熱の実験コンテスト」で受賞
株式会社八光熱が主催する「第9回八光熱の実験コンテスト」において、第1位に入賞しました。
当コンテストは「熱を利用した身近な実験を紹介する」ことをテーマに、2006年から行なわれています。
受 賞 名 : 第1位
受賞実験名 : 電熱製品で綿菓子を作ろう!
受 賞 者 :
国新聞/愛媛新聞未来科学部ロボット・メカトロニクス学科
山崎正博さん(4年)
金子颯太さん(3年)
木原啓太さん(4年)
駒形翔さん(4年)
和田隆行さん(4年)
大野祐人さん(4年)
長岐一樹さん(4年)
詳 細 :
http://www.hakko.co.jp/contest/result_092.php
岩瀬将美准教授 NHK「超絶 凄ワザ!」に出演

ゆっくり走るときに起こりやすい自転車の転倒事故を減らすためにも、「凄ワザ」でゆっくりでも倒れずに走る自転車の実現に挑みます。
挑むのは、手作り自転車職人 ケルビム 今野様と,本学のロボット工学研究者 岩瀬先生と栁田岳瑠、波多野隆馬、谷拓也、清宮悠生の4名の生徒達。幅50センチ、長さ50メートルの一本道を、ハンドル操作をせず、こがずに、どこまで進めるかを競います。
藤川太郎助教 「日刊工業新聞」に掲載
井上淳助教 「歩行リハビリ一人でも -東京電機大が補助器-」
井上淳助教 「片麻痺患者用 歩行訓練補助器」
藤川太郎助教「蝶の構造と飛翔メカニズムを応用した小型はばたきロボット開発」

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の藤川太郎助教が、第4回ネイチャー・インダストリー・アワードにおいて「蝶の構造と飛翔メカニズムを応用した小型はばたきロボット開発」により特別賞を受賞されました。当記事は,日刊工業新聞の特別紙面にて掲載されます。
横山教授 日本政府観光局主催の授賞式に、横山教授が代表として出席

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科 横山智紀教授(電子制御システム研究室)が実行委員として携わっていた「2014 パワーエレクトロニクス国際会議」が、日本政府観光局(JNTO)が主催する「国際会議誘致・開催貢献賞」国際会議誘致・開催の部において、受賞会議として選出されました。
12月9日に開催される受賞式に横山教授が代表として出席します。
井上淳助教 「片麻痺患者用 歩行訓練補助器」

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の井上助教が開発した、歩行補助器が中国新聞,愛媛新聞に掲載されました。 この装置は、片麻痺患者に対し,病棟で安全な杖歩行訓練を可能とする装置で、3年後の実用化を目指しています。
井上淳助教 「空を飛ぶ夢が歩いて走る夢に - そして、生きる目的も変わった」

井上助教が寄稿した原稿が、日本せきずい基金が発行している「日本せきずい基金ニュース」に掲載されました。自身の病気を経て、福祉工学の道に進むまでの体験を紹介しています。
藤川太郎助教「単純なメカニズムで羽ばたく蝶型ロボット」

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の藤川太郎助教が取り組んでいる研究が、科学雑誌のニュートン(2015年4月号)に掲載されました。
自然界の卓越したデザインをロボット設計に活かす「単純なメカニズムで羽ばたく蝶型ロボット」に関する研究で、蝶のはばたきのメカニズムを取り入れた蝶型ロボットが写真付きで掲載されています。当記事は4ページ目、積水化学工業株式会社の広告内でご覧いただけます。
藤川太郎助教 「小型羽ばたきロボット」

生物の体の仕組みを参考にして環境に優しい製品を生み出す「バイオミメティクス(生物模倣技術)」にスポットを当てた企画展「生物のデザインに学ぶ未来をひらくバイオミメティクス」において、アゲハチョウが飛ぶ仕組みを研究して作られた「小型羽ばたきロボット」の写真が掲載されました。
中村明生准教授 「快適な暮らしのためにロボット技術の開発を目指す研究者」

「HR高校進学部 各界のスペシャリスト 大学の先生をズバッと紹介!」コーナーにて、「快適な暮らしのためのロボット技術の開発を目指す研究者」と題して、研究紹介の他、研究室学生のコメント、キーワード、メッセージが掲載されました。
中村明生准教授 「服装の特徴で人物特定システム」

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の中村明生准教授らが開発した、「服装の特徴で人物特定システム」が日経産業新聞に掲載されました。
開発したシステムは、距離データを使用して人物を発見し、画像データから衣服の色や模様を用いて人物の特定を行うものです。
顔情報を使用しないことから個人情報にも配慮しています。
将来的には商業施設の防犯カメラを用いた迷子探し等への応用が期待されます。
中村明生准教授 「障碍者向け音声ガイド装置」

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の中村明生准教授らが開発した、視覚障害者向けに目の前の状況を音声で伝える装置が平成25年11月8日の日経産業新聞に掲載されました。
転倒事故などを防ぐ歩行支援用の医療福祉機器として、民間企業と協力し、3年以内の実用化を目指しています。
中村明生准教授 「文字を”読む”指輪」

平成25年11月5日のテレビ東京の報道番組「ワールドビジネスサテライト」に未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の中村明生准教授が出演しました。
「トレンドたまご」というコーナーで、「文字を”読む”指輪」と題し、なぞった文字を音読する装置が紹介されました。
この装置は、視覚障害者支援のために開発されましたが、視力の衰えた高齢者や弱視の人にも応用でき、5年後の実用化を目指しています。
中村明生准教授 「なぞった文字を音読する装置」

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の中村明生准教授が開発した、なぞった文字を音読する装置が平成25年10月30日の日経産業新聞に掲載されました。
この装置は、視力の衰えた高齢者や弱視の人が文字を指差すと読み上げてくれる装置で、5年後の実用化を目指しています。
石川教授 「パワーアシスト付き車いす」

石川潤教授らが開発したパワーアシスト付き車いすが、日経産業新聞にて「車いす、軽快に片足こぎ」と題した記事で紹介されました。
記事の抜粋
『東京電機大学の石川潤教授らは、わずかな力で大きな動力を生み出すパワーア
シスト機能が付いた車いすを開発した。片足を動かして車いすを移動させる足こぎ式で、足に障害を持つ人も軽い力で動かせる。広い範囲を移動できるようにな
るうえ、リハビリに向けて筋力の低下も防げる。民間企業と連携して2~3年後を
目標に製品化を目指す。』
本学科学生の高倉さんがスカイツリーの模型を製作し、読売新聞に掲載
全長4.2mのスカイツリーの模型を製作し、
9月8日の読売新聞に掲載されました。

神津講師、池内晴香さん、野口遼さん 学会誌で取材記事が掲載
野口遼さん(中村研究室・修士1年)の取材記事「満天の星~コニカミノルタプラネタリウム~」が
電気学会誌(2012 Vol.132 No.8)の十見百聞に掲載されました。
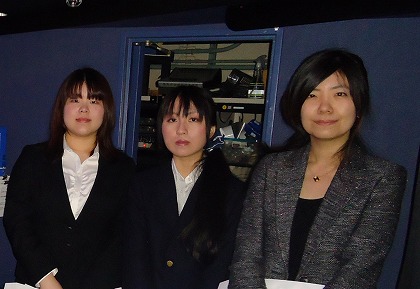
- 電気学会誌(2012 Vol.132 No.8) https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ieejjournal/-char/ja/
- コニカミノルタプラネタリウム http://www.planetarium.konicaminolta.jp/
- 情報化制御システム研究室 http://www.fr.dendai.ac.jp/lab/shiolab.html
- 知能機械システム研究室 http://www.is.fr.dendai.ac.jp/
中村准教授 「どこでもインターフェイス」の研究がテレビニュースで紹介

中村明生准教授らが開発した「どこでもインタフェース」が、
テレビ東京・ワールドビジネスサテライトの特集「リモコン不要の操作革命」に
て紹介されました。
- 知能機械システム研究室 http://www.is.fr.dendai.ac.jp/
- ワールドビジネスサテライト http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/feature/post_24943/
中村准教授 新装置開発 「壁・机が家電リモコンに」

中村明生准教授らが開発した新装置が新聞で紹介されました。
カメラで動作を認識する従来技術を発展させ、CGで作成した操作用タッチパネル
を壁・床などの任意の指定位置にプロジェクタで投影し、その上で行うジェス
チャを認識する仕組みで2年以内の実用化を目指します。
- 知能機械システム研究室 http://www.is.fr.dendai.ac.jp/
岩瀬准教授 NHK「あさイチ」で幼児同乗自転車の実験に協力

岩瀬将美准教授と研究室の学生が、幼児用の座席取り付けた3人乗りの
自転者や重い荷物を載せた場合の自転車の安定性について実験、
解説。
また、今回の番組内の実験には、ロボット・メカトロニクス学科1年生の荒尾さん、小林さん、2年生の川口さんが協力しました。
岩瀬准教授 「3人乗り自転車の開発の最先端」
3人乗り自転車の仕組みや安全性、開発の最先端を紹介する記事の中で、
岩瀬将美准教授の幼児同乗用自転車に関する研究が紹介されました。
記事の抜粋
『東京電機大学未来科学部の岩瀬将美准教授は、実験で重くなったハンドルを、電気の力で軽くする「パワステ」機能を試作した。
ハンドルに付けたセンサーから動く角度を検出。コンピューターで重みを推定してモーターで力を加え、何も乗せていない時と同じようにハンドルを操作できるようにした。
家でも3人乗り自転車に乗る岩瀬さんは「子どもを2人乗せても、乗せていない時と同じような感覚で運転できれば、発進や停止のときのふらつきを減らせる」と期待するが、実用化はまだ難しいという。』
岩瀬准教授 「安全な幼児同乗用自転車を開発」
岩瀬将美准教授の幼児同乗用自転車に関する研究が掲載されました。
幼児用の座席取り付けた3人乗りの自転車や重い荷物を載せた場合でも、楽にハンドル操作ができる自転車向けのパワーステアリング装置の開発について紹介されています。
今後、改良や安全性の検討をし、2012年に試作機を作成し実用化を目指しています。
NHK教育「サイエンスZERO」でIDCロボコン放送
8月6日から18日にかけて本学で行われたIDCロボコンの模様が、NHK教育の科学番組『サイエンスZERO』で紹介されました。
9月12日(土)22:00-22:35放送
*再放送あり:9/17(木)2:30-3:05(BS2) 9/18(金)19:00-19:35(NHK教育)
サイエンスZERO
このほかIDCロボコンの様子がさまざまなメディアで取り上げられました。
- CATV足立
○9/28 IDCロボコン09~あたちの未来に向けて~
動画deあだちで配信中!
○8/18生中継
IDCロボットコンテストの大会を生中継しました。 - NHKニュース
○8/18 首都圏ネットワーク(17:40-19:00)
○8/18 首都圏ニュース845(20:45-21:00)
「世界の大学生集結 ロボットコンテスト」と題して大会の様子が報道されました。 - 東京MXテレビ○8/16 MXニュース(18:00-18:15)
http://www.mxtv.co.jp/mxnews/news/200908166.html
IDCロボットコンテストの製作風景・一般公開・サテライトイベントの様子が紹介されました。 - 朝日新聞
○8/18
「7か国の大学生 ロボットを合作」として掲載 - 読売新聞(江東版)
○7/28
「7か国48人 ロボ作り交流」として大会の予告が掲載されました。 - 日刊工業新聞
○7/27
「7カ国の大学生ロボット競技会」として大会の予告が掲載されました。 - 足立朝日
○8/5
「世界の大学生がアイデアと技術を競う 国際ロボットコンテスト開催」と題して、紹介されました。
Web版も掲載されています。
http://www.adachi-asahi.jp/?p=7194 - 亀有経済新聞
○8/18
Webニュースに大会の様子が掲載
「千住で「ロボコン」決勝大会?各国から48人参加、「HANABI」テーマに腕競う」
http://kameari.keizai.biz/headline/229/ - 教育学術新聞
○8/26
「IDCロボコンを開催 参加国混成チームが10日間で製作」 - ImpressWatch(RobotWatch)
○9/1 大会レポートがRobotWatchに掲載(試合の様子が詳しく書かれています)
http://robot.watch.impress.co.jp/docs/news/20090901_312294.html - ロボコンマガジン
○8/19
Onlineロボコンマガジンに大会の様子を掲載
http://www.ohmsha.co.jp/robocon/archive/2009/08/idc2009.html
「情報キャッチ!!好きです。あだち」
足立区の広報番組「情報キャッチ!!好きです。あだち」で東京電機大学が紹介され、ロボメカも2年生の基礎実験の様子やIDCロボコンについて紹介されています。1月1日から7日かけて放送されました。
「IDC Robocon 2008 in Brazil」

今年も国際ロボットコンテスト(IDC Robocon)に本学科教員の研究室より4名の学生が参加しました。今年はブラジルのサンパウロ大学で開催され、日本、アメリカ、ドイツ、韓国、フランス、タイ、ブラジルから集まった大学生で、混成チームを編成し、ロボットの製作・競技会を行いました。大会の様子がNHKニュースで取り上げられました。また、ロボコンマガジンにも大会の記事が掲載されています。
ロボメカのWebページにも情報がありますので、ご覧ください。
http://www.fr.dendai.ac.jp/education/idc2008/idcblog.html
大園学部長、鈴木准教授 「最先端の研究を語る」


全国の家電量販店などで配布されるフリーペーパー SQUARE ENIX MAGAZINEでの特集”どうなる!? どう変わる!?「近未来」”で、未来科学のプロとして本学科の大園成夫学科長、鈴木聡准教授がインタビューに協力し、大学での最先端の研究、近未来の展望についての話が掲載されました。
石川教授 「生活支援ロボ開発に力」

石川潤教授の生活支援ロボットに関する研究が紹介されました。ロボットと共生する未来の居住空間の開発やコンピュータメカトロニクスに関する研究、技術アドバイザとして参加している対人地雷探知・除去のプロジェクトについても紹介されました。また、ロボット・メカトロニクス学科の1年生で実施している実習授業「ワークショップ」も写真つきで紹介されました。
「国際ロボットコンテストで活躍」
タイのバンコクで開催された国際ロボットコンテスト(IDC)に本学科教員の研究室より4名の学生が参加しました。IDCは日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国、ブラジルなどから集まった大学生を、各国混成の4人チームに編成し、10日間でロボットの製作を行い、競技会を実施するものです。本年はタイとの修好120周年記念の公式イベントとしても開催され、大会の様子が複数のテレビニュースで取り上げられました。
古田教授 「春の園遊会に招かれる」

古田勝久教授が4月26日(木)に開かれる『春の園遊会』に、政界はじめ各界の功労者共々、招待されることとなりました。 「人道的対人地雷探知・除去技術研究開発推進事業」研究総括としての貢献を高く評価されての園遊会招待であり、NHKニュースで招待者として紹介されました。
